教えて武田先生!第4回「共通テストを軸に入試対策を考える」
こんにちは。あおい予備校スタッフのHです。
新学期が始まって半月余り。そろそろ落ち着いて勉強に取り組む時期となりました。
当塾でも先日から前期授業が開講となり、新規入塾の生徒さんも少し緊張しながら授業に参加しています。
あおい予備校校長の武田先生に受験生や保護者の皆さんが知りたい情報をお伝えする「教えて武田先生」第4回は「共通テストを軸に入試対策を考える」がテーマです。
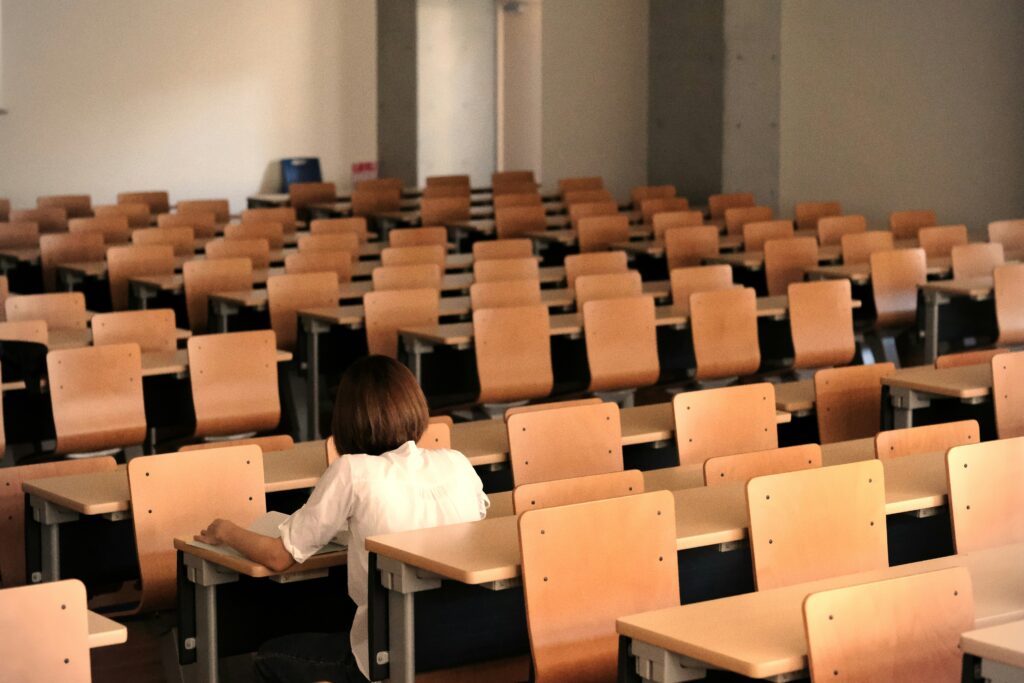
スタッフH(以下H):いよいよ新年度がはじまり、まだ授業に慣れていない生徒さんもいて少し教室内は緊張感がありますね。毎年のことですが。
武田校長(以下T):そうですね。教える私もそうですが、いつも初回の授業はドキドキします。
H:武田先生でもそうなんですね。驚きです。ところで、先生、各大学の入試情報をあたっていると、ずいぶん共通テスト利用の大学が増えていますよね。しかも一般選抜で共通テストを受験していないとそもそも受験資格がないという…
T:早稲田大学がその典型ですよね。2021年度入試から政治経済学部が共通テストの「英語」「国語」「数学1A」及び選択科目(理社から1科目)を必須化し、2月の試験で論述問題を課すことになり、大きな話題を呼びました。その後、国際教養学部や社会科学部など他学部にも共通テスト受験必須化が広がりました。それから上智大学、立教大学、青山学院大学でも共通テストが必須化されています。
H:受験のハードルが上がった分、受験者数は減ったのではないですか?
T: 確かにそうですね。共通テスト必須学部は軒並み志願者が減りました。ただし、この改革が功を奏し、入学者の質が上がったと言われています。
H:そうなんですね。
T: 「データ活用」を重視する世の中の流れとも一致するのですが、多くの大学で履修が必要な科目として統計学があります。統計学は数学ⅠAで扱う内容がベースになっています。高校数学の基本レベルを習得していないと大学の授業についていけないという可能性もありますね。
H:私は大学では経済学部だったので、数学が苦手な学生は苦労してた記憶があります。
T:結局、入試問題は高校の学習成果がどれくらいあるのか、大学で学ぶためにどれくらい準備ができているのか、それを見ているのです。共通テストの問題はどの科目にもそれが反映されていると思います。
H:なるほど。よくわかりました。
T:マーク式の模擬試験も共通テストのフォーマットになっているので、受験勉強はやはり共通テスト対策を軸にすすめていくべきでしょうね。今や共通テストは、国公立大志望者専用の試験というわけではありませんから。
H:共通テスト対策はまず何からはじめたら良いでしょうか?
T:共通テストは2021年からはじまっているので、過去問は5年分あります。まずは過去問に目を通して、何が問われているのかを理解するようにしてください。試験の意図をしっかり把握せずに、やみくもに暗記に走るのは効率的ではないです。
H:なるほど。
T:塾や予備校の授業というのは、その意味で非常に効率的だと思います。最終目標から逆算して、今何が必要なのかを教えてくれるからです。高校の教科書の内容を入試問題が解けるように再構成してくれるというイメージです。
H:本当にそうですね。今回も参考になるお話、ありがとうございました。
今回のまとめ:共通テストで高得点を取ることは、大学入試においてますます重要になってきています。短期集中型の勉強ではなく、問題の意図や特徴を理解しながら力をつけていきましょう。



